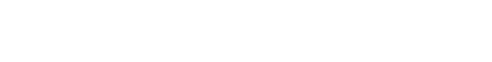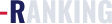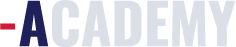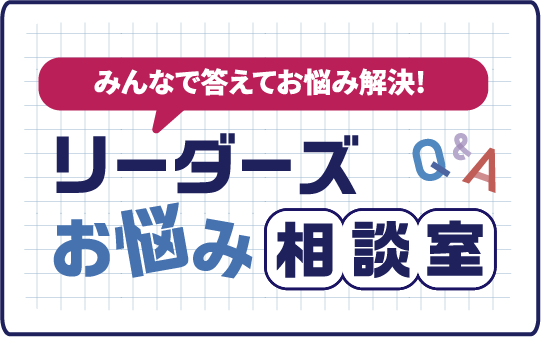医療崩壊の報道から想うこと~回復期リハ病院の機能分化を~《斉藤 秀之氏連載シリーズ vol.3》

1都3県の緊急事態宣言が2週間延期となったにもかかわらず、都内の20時までの賑わいは「3密」などどこ吹く風のように見えるときもある。あたかも、自粛・変異株・ワクチン配給に対するアンチテーゼのような「3蜜」を探しているようである。残念ながら、この国の行方を心配するばかりである。しかしながら、歴史の1ページを刻むことになるCOVID-19と人類の闘いは、まだまだ続くことであろう。ここは腰を据えて、原理原則に基づいて、皆で覚悟を決めて、”見えない手ごわい強かな敵”と相対していくしかない。
さて、前回は「COVID-19による医療崩壊の報道から想うこと‐急性期‐」という内容を回想した。リッチな急性病病院もおけるCOVID-19患者の受け入れ態勢とそのリハビリテーション機能の強化は必要であることをお伝えした。しかしながら、法やヒエラルキーにより既知として進まないわが国で、回復期リハビリテーション病院が制度化され、早期受け入れが目的の1つであったはずと結んだ。
回復期リハビリテーション病棟は介護保険制度と同時に制定されたリハビリテーションの市民権を真の意味で獲得した制度であった。その目的は、「ADL回復」「家庭復帰」であり、より早く受け入れて急性期での寝たきりを防止すると同時に、発症後速やかに専門的なリハビリテーションを重点的に投入し、早期自宅復帰を具体的にするためのイノベーションをもあった。一時、急性期からの転院可能の判定から実際の受け入れまでの「入院待機日数」が当該病棟の質マネジメント指標となったこともある。筆者はこの指標こそが連携の質を表し、急性期病院も回復期リハ病院もそれぞれその質を高めることの帰結だと思っている。
つまり、急性期病院がより早期に回復期にリハ病院に転院できる状態への治療を行い、回復期リハ病院がより早期に受け入れ、それぞれが病棟稼働率を高め、急性期は救急救命を断らない構えをとることができ、回復期リハ病棟はリハビリテーションを必要とする患者を断らない構えができることになる。無論、急性期の病床数よりも回復期リハ病院の病床数は多いことが前提となる。

そこでCOVID-19下ではどうか。
急性期での退院基準は、「発症10日以上、軽快後3日以上」と厚生労働省が基準を出したことは久しい。急性期病院は、転院先となる後方支援病床を確保できればコロナ患者を主に診療する大病院(急性期病院)の医療効率が高まるという主張をする。それは前段で述べた通りその通りである。一方、当初クラスターが回復期リハ病院で発生したこと誘因かもしれないが、受け入れに慎重という風潮が報道されてからも、回復期リハ病院での受け入れは容易ではないことが正義となっているように感じた。 回復期リハ病院の受け入れができないということは、寝たきりを作りことになることは自明である。にもかかわらず、介護老人保健施設が受け入れ先になっている風潮も本末転倒のような気がします。この解決のためには、病院環境はもとより、回復期リハ病院に勤務する各専門職が従来の技能にとどまらず、COVID-19患者への対応、感染管理下での新たな専門技能を身につける必要がある。
技能は経験しなければ身につかない。つまり、受け入れていかないとCOVID-19下の回復期リハ病院やそこで受持する専門職の経験値は生まれないのである。感染管理下だけにとどまらず、「ADL改善」「自宅復帰」を目指すCOVID-19患者専用の回復期リハ病院あるいは病床を地域で整備していくことを提案する。そして、場合によっては人を派遣したり、物を貸し出したりと、全国各地でCOVID-19患者専用とその他の患者の回復期リハ病院を機能分化してはよいのではないか。
現場を離れて久しい筆者の独り言であり、お叱りを受けることは重々承知している。しかしながら、今こそリハマインドを示すときでなはいだろうか。そして、回復期リハビリテーション病院の矜持を国民に示し、イノベーションを皆で起こした時の思い出す絶好の機会ではないだろうか。
執筆:
斉藤 秀之(さいとう ひでゆき)
(回復期リハビリテーション病棟協会PTOTST委員会委員長 筑波大学グローバル教育院教授)